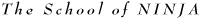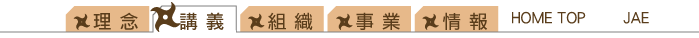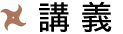心編
(B)忍の思想
(2)武士道外の道
さて、本稿では歴史を掘り下げるのが目的ではありませんので、この辺でとめておきますが、大切なのは武士が政権を担うにつれて、タテマエ第一のサラリーマン武家社会が完成し、主従関係をタテ軸に奉仕、精錬をヨコ軸にした武士道が育まれていったことです。
そこでは「騙すこと」、「卑怯であること」、「裏切ること」は最も嫌われました。
しかし、武術というものは、もともと目的達成のための合理的な考えとして、「自立」と「騙し」の法を内包しており、それらが「悪」であるという概念は無いのです。
当然、体制に与することのできない武術や武術家ははみ出していったわけです。
武芸者の大道芸的剣術、剣以外の小武器術、僧侶や修験者の薙刀や棒術などはそうでしょう。
その他、武術ではないのですが、修験者の調伏法や幻術、売薬、マタギの狩猟、遊行僧の行脚、能や田楽などの芸能なども何かよく理解できないものとして、同一地平線上に存在しました。
私はそこに忍者集団が生まれてくる土壌があったと思うのです。
それぞれの細かい分析は後回しにすることにして、その土壌についてざっくりと大雑把に特質を抽出してみると以下のようになると思います。
特殊な技術、芸能を持っている。
大自然や何らかの神々を信仰している。
合理的な思考を持っている。
自主、独立の気風がある。
閉鎖的社会を形成する。
情報交換組織または互助ネットワークを持っている。
雇用主から契約で雇われる。
さて、意外な結果に驚かされます。
これらは現代ではごく当たり前の特質で、それほど特殊なものではありません。
例えば中小企業にはこうした特質を色濃くもつ優秀な会社がいくつもあります。
中には独自の技術を持って、競合する複数の大企業の下請けを同時に行う専門技術会社もありますし、独自の通販ネットワークで巧みに生き抜いている会社もあります。
幕府や大名が忍者を雇うということも、大企業が優秀なスペシャリストを契約社員にしたり、人材会社から派遣を受けたりすることだと考えると理解できます。
こうしてみると、忍者集団が被差別民から発生したとか、裏社会の人間であるとかのイメージが間違いであることが想像できます。
忍者は一律に主君に奉公する武士道社会とは対極をなす自立した特殊技術者集団であり、室町時代末期から戦国時代にかけて、疾風怒涛の世間をいきいきと自由闊達に動き回っていたかの感さえあります。