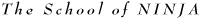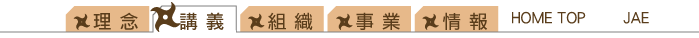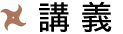心編
(B)忍の思想
武門の「武」は武士階級の勃興とともに、古いもの、雑多なものを振り落としながら、江戸時代から明治時代にかけて、珠玉のような武士道へと昇華していきました。
ここで、古いもの、雑多なものといいましたが、これらは本当に振り落とされ、歴史の波の中で消滅してしまったのでしょうか。
私はこのグループの中に「忍の思想」のヒントになる「何か」がありそうな気がしてなりません。
(1)武と呪
武門の最初の大将軍は坂上田村麻呂(758年〜811年)という平安時代の武官です。
征夷大将軍として現在の岩手県、秋田県あたりまで、遠征しし、朝廷に隷属させました。
夷とは蝦夷のことで、朝廷に服さない人々のことで、先住の狩猟民やアイヌ系の人々だったといわれています。
これを征服する武官の長を征夷大将軍といいます。
因みに、征夷大将軍というの、武家の棟梁が位に就き、朝廷から任命されました。その征夷大将軍が常駐するところを幕府といいます。
源頼朝以降、実質的には日本の君主の資格のひとつです。
しかし形式的には、あくまでも天皇が日本国国王であるわけです。
どうして諸武家が天皇家を倒して、覇権を取らなかったのかは世界史的にはとっても不思議なことなのです。
ただ一人、織田信長が生きていれば、そうしたかも知れませんが、本能寺の変で殺されてしまいました。
それに関係があるかどうかは分かりませんが、例えば朝廷の臣の役割を文官と武官に分けたり、武士の教養を文武両道といったりしまが、ここで私が注目するのがこの「文」、「武」というのは天皇家の役割ではなかったということです。
実は天皇家の役割は「文」でもなく「武」でもなく「呪」なのでした。
「呪」というのは宗教的儀式によって祖先を祀り、呪法によって国体を護るということです。
日本のあらゆる宗教は天皇家直属なのです。
つまり、天皇は神社やお寺、修験道、陰陽師の総元締めだったのです。
いかに、戦国の世を勝ち抜いた大名といえども、このネットワークを敵に回せば一瞬のうちに崩壊します。
徳川幕府は長い時間をかけて、巧妙に朝廷の力を削いできたのですが、最後は官軍の振りかざす天皇の「錦の御旗」に手も足も出せず崩壊しました。
従って、朝廷には「武」などというものは、そのとき強い者に任せればいいという考えがあって、当時、征夷大将軍は臨時職に近い、それほどは大した役職ではなかったようです。
坂上田村麻呂も現在の奈良県高取町辺りに住んでいた「東漢氏」の一族出身で、帰化人であったといわれています。だからこそ、東北まで遠征できる武力があり、知識があり、技術があったのだと思うのです。
つまり朝廷は田村麻呂を軍事のプロフェッショナルとして雇ったのではないでしょうか。
ここで思い出されるのが、京の武士団は武芸ということに長けた、田楽や能などと同様の特殊芸能者として扱われていたという説です。
帰化人の持つ先進技術や武芸、山の民の鉱山技術、夷の狩猟法、遊行者の芸能、修験者の情報収集、呪法、医療、薬草知識などは、割と朝廷に近いところに、ひと塊か、もしくはネットワーク状に専門集団を形成していたのではないでしょうか。
彼らの特長は「特殊技術を持った自立した個人または集団で、雇用主とは臨時雇用契約を結ぶ」ということです。
朝廷はこれらの集団に何らかの繋がりを持っていたのではないでしょうか。
例えば、俘囚(朝廷に服した夷の人々))であった安倍氏の後を継ぐ奥州の藤原氏がみちのく金山の黄金を背景に朝廷と特別なネットワークをもち、鎌倉の頼朝と対決し、義経を匿ったという歴史はそのあたりのことを連想させます。