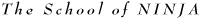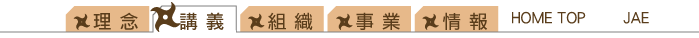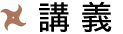心編
(A)日本の武道
(1)武術の起源
1.古代世界の武術
人間対人間が徒手または武器を持って戦う格闘技というのは紀元前の古代世界の各地にあったようです。
レスリングやボクシング、インドのカラリファイヤット、中国のカンフー、少林寺、日本の相撲、琉球唐手などそれぞれ特長ある格闘技の発生が認められます。
ボクシングは紀元前4世紀頃のエジプトに似たような格闘技あったといわれていますし、レスリングは古代ギリシャ時代から、オリンピックの主要種目の一つでありました。
しかし、東洋の格闘技と西洋のそれではその後の発達において、著しい差が認められます。
西洋がキリスト教の影響で格闘技を軽視していったのに比べ、例えば古代インドでは精神と肉体との調和という考え方があり、格闘技の鍛錬は、精神は精神集中、肉体は医療的知識が不可欠と考えられ、その上でたゆまぬ訓練と、武技や武器の使い方に習熟することが求められました。
これは6世紀にインドのクシャトリア階級出身のインド僧菩提達磨が嵩山少林寺に滞在して、拳法を伝えたとの伝説とつながります。
この法は僧侶の心身の鍛錬のための養行で、強力な護身法であったといわれています。
日本の相撲は、神道の豊穣の儀礼を起源としているといわれています。タイのムエタイの試合前に見られる踊り �「ワイクー �」も、神に祈りを捧げる神聖なものです。
つまり東アジアにおいては、格闘技は敵を倒すことが目的というだけでなく、宗教的修行や自己の鍛錬法としての意義付けがなされてきました。
そして技術は師から弟子にと伝えられ、伝統を重んじ、武技の使用においては制限がもうけられました。
2.中国の武術
中国では、秦の統一が紀元前255年。その頃には武人の鎧も進化し、集団の戦闘が行われていたわけですから、大規模な戦の勝敗に関しては個人技の武技はそれほど重要な意味を持たなくなっていたと思われると同時に、平時においては文民政治で武技は軽視されていたことから、一種の自己鍛錬法であるというスタンスが必要であったのでしょう。
戦場では弓や剣、槍などで、突く、払う、打つなどが主体であったと思われます。
徒手や棍で突く、打つ、蹴る、投げるなどの基本技を組み合わせ、相対で修練するような体系は、やはり河南省の嵩山少林寺の僧兵たちの拳法に始まるというのが一般的です。
度重なる群盗の襲撃に対抗するため僧たちが武装したとも言われています。
トンファ、ヌンチャク、サイ、等は農耕具を改良して武器にした物です。
8世紀に入ると、道教などの興隆で少林寺が衰亡し、門外に技術が流失しました。
明(14世紀)の頃、「水滸伝」という武侠小説が生まれます。
北宋末期の汚職官吏がはびこる時代に、腕に覚えのある英雄好漢が梁山泊に集まって、国を救うことを目指すという物語です。
ここには武芸を好む往時の好漢たちの姿が生き生きと活写されています。
九紋龍史進は武芸十八般の達人、花和尚魯智深は強力無双で、拳骨3発で敵を殺してしまう。なんやらかんやら、こんな連中が108人も集まるのですから、面白い話です。一度読んでみてください。
水滸伝は中国の民衆に受け入れられ、何百年にわたって物語はふくらみ、日本の講談小説にも大きな影響を与えました。
これによって明代には武芸というものが武人や民衆の間に根を張っていたことが想像できます。
「武編」、「紀効新書」、「武備志」などという武芸書も次々と著されました。
清代(1616〜1912)に入ると多くの武人たちが野に下り、一気に民間に武術が広がり、中国武術の有名な門派もこの頃に成立しました。
内家拳系統では河南省陳家溝の陳氏太極拳、そこから発展した楊氏太極拳、山西省の形意拳、八卦掌、八極拳。そして外家拳では少林寺に源を発する少林拳の系統。南派拳系統の洪家拳、ブルースリーの学んだ詠春拳などが有名です。
3.日本への影響
これらの門派の成立により、中国武術はそれぞれ独特に、より精緻に体系づけられていったわけです。
日本武術への影響はいくつかのポイントが考えられます。
ひとつは沖縄唐手の源流、首里手は明らかに中国の南派拳術の流れであろうということ。
柔術もその発展過程のなかで、明から帰化した陳元贇 (1587〜1671)から影響を受けました。
この人は寛永二年(三九歳)のころ江戸へ出て、良移心当流和(やわら)を創始した福野七郎右衛門らの柔術家と接触して、彼らに少林寺系の中国拳法や接骨術・「十手」の使用法を伝授したと伝えられています。
その他古流柔術各派と中国武術の交流もいくつか認められます。
おそらくは経絡医法を活用した当身系、捻る、固めるなどの関節系など取り入れたと考えられます。
また、中国武術の武器も流入したことも、想像できます。