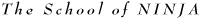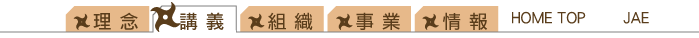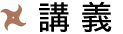心編
(A)日本の武道
(2)武道の成立
格闘技術を武術と規定すれば日本武術の起源は古代までさかのぼります。
日本書紀に当麻蹴速(たいまのけはや)と野見宿禰(のみのすくね)の力比べの話が記されています。これが現代の相撲の起源といわれています。
「垂仁天皇は、力自慢の大和の當麻蹶速と出雲の野見宿禰とを天覧試合で力比べをさせました。蹶速は宿禰に脇骨を蹴り折られて死んでしまいました。」とあります。
蹴り折られるくらいだから、現代の相撲とはだいぶ異なり、突きや蹴り、関節技なども含まれていたのでしょう。
野見宿禰(のみのすくね)は抱えられ土師姓となり、子孫は菅原姓を賜りました。菅原道真はその子孫です。
相撲はその後、神事、祭事に組み込まれ、現代まで存続していくわけです。
戦場では、弓や薙刀、太刀が主体の集団戦闘になっていくのですが、やはり最後は相対で組討ちし、生死を決することになります。
この組討術の研究が古柔術の起源であったと考えられます。
さて、しかしながら、日本の武道の代表はやはり剣術ということになります。
剣は武士の必携武器であり、一種の神秘性もそなえているからです。
武士の発生は諸説ありますが、専門職としての武士の確立はおおむね10世紀以降ですから割合に新しい職業なのです。
日本の初期武士団は大まかに見ると二つの系統に分かれます。都の京を中心とした武士団と関東の武士団です。
中沢新一氏の説によると、西国の武士達は武芸のプロということで、田楽や能などと同様の特殊芸能者として扱われていた。
一方、東国の武士は主君と主従の関係を築き、どのように手柄を上げ、報酬をもらうのかという倫理観を育ててきた。
ということですが、この違いは剣術の初期流派の分類においても同様の感覚があったようで、西の京八流、東の鹿島七流と称されています。
剣豪のことを初期の頃、武芸者とよんだこともこれで納得がいきます。
京八流というのは、平安時代、伝説の兵学者、鬼一法眼という人が鞍馬の僧たちに剣を教え、その中に八人の達人がいたという故事に因む流派で、鞍馬八流ともいわれました。
鞍馬流、諏訪流、吉岡流などがあったとされていますが、詳細は詳らかではない。
吉岡一門はのちに宮本武蔵と対決したことで知られています。
鹿島七流は「鹿島の太刀」を伝える常陸の国鹿島神宮の神官卜部家を中心とする七家のことです。
鹿島の太刀とは、仁徳天皇の時代、国摩大鹿島命の後裔、国摩真人神の啓示によって神妙剣と称する刀術を創業したと伝えられるもので、その流派は、良移流、鹿島流、香取流、本心流、ト伝流、神刀流、日本流といわれます。
卜部家からは塚原卜伝(1490〜1571)が生まれています。
源流を同じくするお隣の香取神宮からは日本最古の武術流儀であるといわれる天真正伝香取神道流が生まれています。
開祖は香取郡飯笹村に生まれた武将、飯篠長威斎家直(1387〜1488)です。
伝承されている技術は剣術、居合、柔術、棒術、槍術、薙刀術、手裏剣術等で、さながら戦国時代の実践武術を髣髴させる厳しい武道です。
日本の剣術諸流派はここから、派生したとも言われています。
室町時代末期の三代流派この香取神道流と、愛州移香斎の陰流、中条兵庫頭長秀の中条流です。
愛州移香斎久忠(1452〜1528)は三重の人、九州鵜戸の岩屋にこもり愛州陰流をひらきました。
愛州陰流は上泉伊勢守信綱により、新陰流となり、柳生石舟斎の柳生新陰流の源流となります。
中条流は中条兵庫助長秀(?〜1384年)によって創始されました。剣術以外にも小太刀や槍術の技術も伝える総合武術でした。
後代の富田勢源によって普及された事から、富田流とも呼ばれます。後の一刀流の母体ともなりました。
さて、難しい流派の名称を覚えるのが本稿の目的ではありません。
問題は室町時代末期になぜこれほどの流派が誕生したのかということになります。
ひとつは戦乱の世を迎えて、武士階級が社会の表舞台に登場したことです。
そして武士にとって戦いの技術の習得は、自己の生存に関わる最重要なことであり、かつそのための目的意識を明確に持たなければなりませんでした。
そのための武術教習所が必要になってきたということです。
もうひとつは1575年の長篠の合戦において、織田信長の鉄砲隊が武田の最強騎馬軍団を打ち破ったことです。
このことで、戦闘力としての個人剣術の時代は終わりました。
つまり専門職軍隊のはじまりです。一兵卒が戦場で命を懸けて刀を振り回しても、たいした戦利品や報酬は得られなくなってしまったのです。
剣術を習う者はその技術を磨き出世をするか、権威を身につけて有名になり、どこかの大名に師範として雇われるか、自分で道場を開いて生活することを目指すようになったのです。
そのため武術教習所は、師から弟子へと伝える秘伝や教義をもって権威づける必要が生じてきました。
従って、この頃、有名な剣客が数多く輩出し、自らの流派を立ち上げていきました。
技術面では鎧や子具足の上から刺したり、組討ちしたりする戦場用剣術から平服での剣術に変わりました。
そして稽古が安全にできるように修練方法も体系づけられていきました。
細かい実戦用の小武器類は淘汰されていきます。
さて、ここで本題に少し触れておきたいと思います。
武士という職業に武芸は絶対条件であったわけですが、いいかえれば、「武芸をもって、人を殺すことを生業とした専門職」であったということです。
しかし武家社会が成立すると、上から下まで人殺しの専門集団では政治が成り立ちません。
政治を司る武士、管理をする武士、経理を担当する武士が必要になってきたのです。
サラリーマン武家社会を構成する武士たちの必須習得技芸である武術に、権威や倫理を付加して運用に広がりを持たせ、かつ武技の使用に制限を加えなければなりません。
ここにおいて、剣術は剣を学ぶ道、剣をもって心身の鍛錬を行う道、すなわち剣道という「道」へと進化していき、武士道成立の萌芽となります。
しかし、もともとあった「人殺しを業とする武芸専門職能集団」はどこへいってしまったのでしょう。
近年の考え方のなかには武士の源流を狩猟民や俘囚の人達であったとするものもあり、特に西では武士を武芸者と呼び一種の特殊芸能者としてとらえていたことからも、この古武士団のコアの層が消滅したとは考えにくいのです。
東を中心とするサラリーマン武士団と枝分かれしたこの武芸武士団は、もしかすると忍者の成立と深い関係にあるかもしれません。