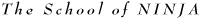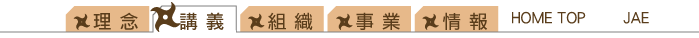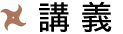心編
(A)日本の武道
(3)武士道とは
近年、世相が乱れていることから、日本の武士道精神を復活せよとか叫ばれていますが、この武士道とは一体どんなものでしょう。
武士道というくらいですから、武道とどういう関係があるのでしょうか、それとも武士の倫理という意味になるのでしょうか。
それにしても現在は武士という職業が存在しないのですから、武士階級が育んだ倫理観や精神を現代に応用せよという意味でしょうか。
大変、難しい問題なのですが、ここで簡単に考察してみたいと思います。
1、新渡戸稲造の「武士道」
武士道、武士道と叫んでみても、21世紀の現代人にはなんだかよくわかりません。
実際にテキストに使ったのは、新渡戸稲造が明治33年(1900年)に発刊した『武士道』(BUSHIDO: The Soul of Japan)とうい本です。
これは日本語訳が出版されていますから、読んでみてください。
敬虔なキリスト教徒であった新渡戸が西洋の道徳観の根底にある騎士道精神に対比して、日本固有の思考や行動の元になる観念を探り出したのが武士道という倫理道徳観です。
武士道は長い封建制の中で武士階級が育み、仏教、神道、儒教の強い影響をうけて完成された観念です。
これが武士階級に限らず日本人、または日本国全体の精神の根底をなしているという主張です。
「義」、「勇」、「仁」、「礼」、「誠」、「名誉」、「忠義」などが武士道の骨格を成す、徳目です。
「義」とは裏取引や不正を憎む正義の心
「勇」とは正義に基づいて行動する勇猛心
「仁」とは力ある者がもつ優しい母のような徳
「礼」とは他人に対する思いやりを表現すること
「誠」とは嘘、ごまかしをしないことに高い敬意を払うこと、
「名誉」とは先祖の名を汚さないため命よりも大切なもの。
「忠義」とは自分の主君に対する絶対的な服従。
これらの徳目が現代の日本人に必要なことは明らかでしょう。
しかしながら武士の道という観点からすると「忠義」に関しては若干の考察が必要です。
少なくとも、室町時代末期までは武士の主君に対する忠義心は薄かったからです。
主君と郎党との関係は一種の契約関係であり、忠誠心は報酬という対価によって保証されていたのであり、主君が弱ければ主君を変えることも、自らが名乗りをあげることもそれほど異端の行動ではなかったのです。
2.剣と禅
柳生新陰流に柳生但馬守宗矩(1571〜1646)という人がいます。
徳川秀忠、家光の将軍家師範としての江戸柳生の地位を確立した剣豪政治家です。
臨済宗の禅僧沢庵と親交があり、この沢庵和尚が柳生但馬守宗矩に書いた手紙が「不動智神妙録」です。
これは大変、難しいのですが、簡単にいうと、武士が剣の修業をし、最高レベルの段階に達したとき、どのような境地に至るのか。生死をかけた場面において、「心」の持ち方はどのようであるべきか。
「集中する心」と次の段階である「とらわれない心」について述べています。
現代の剣道家でも、この文書を愛読する人は多いのです。
宗矩もこれによく理解し、状況を的確に見抜き、無用な争いを避けるという姿勢を貫きました。
人間を殺すための剣術が、人を活かし、世に貢献する手段になる、これが活人剣の思想です。
これが彼を剣士としてばかりでなく、政治家としても徳川幕府の安定に尽くし、優れていたという評価につながります。
沢庵和尚に出会う前の若き宗矩は、没落した柳生家の跡取りであったが、家康に見出されて謀略工作を担わされます。そして全国の大名に門弟や親族を送り込んで情報を集める忍者の元締めのような仕事をしていたといわれています。
現代の小説やドラマで冷たいフィクサーのような役回りで登場するのはその辺りが原因でしょう。
時代は下って、江戸末期に山岡鉄舟(1836―1888)という人が登場します。
剣と禅ということを述べるときには欠かすことのできない達人です。
北辰一刀流の使い手、講武所で千葉周作にも師事。
のちに小野派一刀流を継承し、一刀正伝無刀流(無刀流)を開きました。
有名なエピソードがあります。
明治元年(1868)、謹慎中の第十五代将軍徳川慶喜の恭順の意を、駿府の官軍総督府の西郷南洲へ伝える使者の役を担って、官軍の真っ只中を通り抜け、西郷隆盛と会談。江戸無血開城への道をつけました。
江戸総攻撃を控え殺気立つ敵陣の中を堂々とゆく鉄舟に、官軍の兵士はあっけにとられ、道を開けました。
のちに西郷隆盛は鉄舟について「金もいらぬ、名誉もいらぬ、命もいらぬ人は始末に困るが、そのような人でなければ天下の偉業は成し遂げられない」と賞賛したそうです。
これを無我、至誠の境地というのでしょう。
人を殺すための剣の道はこの2人の剣聖にもみられるように、禅という宗教と化合することにより、「剣の道」から「人の道」に変わっていったのです。
一説によれば武士の生き方を武士道と名づけたのは鉄舟だったといわれています。
3.葉隠
ちょっと変わった武士道について述べてみたいと思います。
それは葉隠です。
「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」あまりにも有名な一文です。
葉隠は江戸時代中期、肥前国鍋島藩藩士、山本常朝(1659〜1719)の武士としての心得について見解を記録したものです。
これはさまざまな人がいろいろな意見をのべていますが、複層的なところもあり、難解です。
そこで自己流な解釈になります。
定朝は敬愛する主君である鍋島光茂が死んだときに殉死をしようとしたが、禁止されていたので出家しました。
つまり、死ぬことが主君に対する奉公だというのです。
「ある武士の一日の始まりは、目が覚めた時寝床の中で先ず自身最大の敵を想像し、壮絶な戦いの末死を遂げて先ず死んだ所から一日が始まる。」
その心構えで、鍋島藩の藩士は「島原の乱」の時、弱体化している武士と死をも厭わないキリシタンの戦いで苦戦している幕軍のなか、大活躍をしたと言う話が伝わっています。
簡単に言うと自分が武士として存在している以上、主君が死ねば無条件に死ぬ。戦が始まれば武術の腕が立とうが立つまいがワーッと前に出て、暴れまくる。当然死ぬ。これ以外に武士であることの意味はない。
しかし、江戸時代も中期になれば戦もない、殉死も禁止。だとすれば常に死と隣り合わせの日常を送るのが武士の本分である。
主君が自分に対して冷淡であったりするときこそ、命を投げ出して真の報恩を尽くすべきだ。主君が自分のことを知る必要はない。この報恩の心は一方通行である。というものです。
この没我的な奉公心は忠節のフリをする武士、言い訳をする武士、卑怯な振る舞いをする武士を根底から否定します。
この「忍ぶ恋」は主君に対するものです。これは武士の生理的感覚です。
みなさんのなかにも自分に対しての主君的な人、例えば社長や師、親分に対して同様な感覚を感じている人も多いことでしょう。
ですからこれは国家のような抽象的存在に対するものではありません。
しかし、こうした純粋な感性は、国家を天皇という人格に置き換えた場合、大きな動きをまき起こしてしまいます。
吉田松陰の天皇への思いや昭和維新を図り決起した青年将校たち、最近では三島由紀夫の自決まで、情念の部分で葉隠の強い影響があったと思われます。