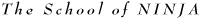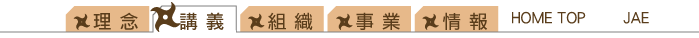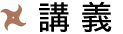歴史編
(2)忍者と修験道
山伏というのを知っていますか。
おでこに頭襟(ときん)を乗せ、結袈裟(ゆいけさ)を首から下げ、錫杖(しゃくじょう)を持ち、ほら貝を鳴らす特異な姿を写真などで見た人がいると思います。
この山伏が修験道の行者の姿です。
伝説上の天狗やカラス天狗もこの格好を模しています。
修験道というのは山岳信仰を母体に密教、神道、道教、陰陽道などが混合されて形成された日本独特の呪術宗教で、江戸時代まで日本の宗教界に大きな地位を占めていました。
古来、山は特別、神聖な場所でした。
神々は山に降りてきたり、山奥に住まわれていたと考えられていたからです。
これを山岳信仰といいます。
この頃、奥深く山に入り、神々に触れ合い、自分の霊力を高めようとした人々がいました。これが修験道の始まりです。
修験道の祖は役小角(えんのおずな)といわれる人です。
ほとんどが伝説に包まれた人ですが、699年に66歳で伊豆の島に流されたと記録されています。
役小角が単純な山岳信仰行者ではなかったことは確かです。
この人の周囲には帰化人が多く、仏教に加えて大陸の道教、陰陽道の影響も強く、高度な呪法もありました。
その中でも、おそらくは特別な霊力を持つ呪術者であったと思われます。
呪術者というのは、山中にて厳しい修行をして、神々と交渉し、個人の霊力を高め、その能力をもって、人々に不可思議な力を示したり、病気治癒などの施術を施す人のことです。
役小角は大坂、奈良の県境にある葛木山に住んだといわれています。その他に、白山修験道の開祖、泰澄(たいちょう)(682年生)が有名です。
霊力によって、空を飛んだり、物を動かしたりことができたと伝えられています。
出羽修験道の伝説の行者、能除(のうじょ)、九州の英彦山の法蓮(ほうれん)、箱根修験道の万巻(まんがん)など全国各地に有名な行者がおられました。
これらの不可思議な能力を誇る修行者がなす修験道は、貴族の間でもてはやされ、やがて武士階級に浸透し、江戸期に入ると天台宗、真言宗に帰属させられるものの、庶民の間に圧倒的な力を持ち続けました。
この修験道を行じる山伏が忍者の起源に関わるという人は多い。
少なくとも山伏は当時、最高の科学といわれた密教や陰陽道に通じ、かつ自ら山野を駆け巡り、呪文を唱え、心身を統一する修業は忍者の訓練と通じるところがあるからです。
また国と国とをふさぐ山岳地帯を棲み家としているので、誰も知らない道や地形を熟知しており、国から国へと自由に往来することができる。
時には、その薬木、薬草の知識から全国各地に薬の行商に出かけたり、本業の信仰流布や祈祷で回ることもできたのです。
源義経が奥州の藤原氏を頼って落ちのびるとき、弁慶が山伏に変装した有名な話はうなずけることなのです。
当時からすれば、他国のことは別世界ですから、その土地の権力者が山伏に情報を求めることは当然のことでしょう。
また前もって情報収集を依頼されることも多かったはずです。
この修験道の開祖達にまつわる空を飛んだり、鬼を使役したりする不可思議な能力と実際に強靭な体力で山野を駆け巡り、かつ自由に全国を渡り歩くことのできる能力は、現在の我々が思う忍者のイメージと一致しています。
もうひとつ、重要なことがあります。
山伏達は修験道の行者として、国家権力に非常に近いところに位置しながら、一方では国家権力の及ばない山の民との交流があったといわれていることです。
山の民については多くの学者が研究していますが、おそらくは農耕民族系の大和政権とは溶け込まずに、集団で山に入った先住民族もしくは非農耕系民族(狩猟系民族)ではなかったかと想定されます。
彼らの特長は山の暮らしに必要な狩猟や薬草治療、炭焼き、金属採掘、木工などの優れた知識と技術を持っていたことです。
山伏は山に入ったときに、こうした山の民と親しくなり、交流をもって、山奥に修行拠点を築くことができたわけです。
里の人間が山伏に一種、異様な畏怖感を感じるのはこうした異文化の匂いがしたからかも知れません
こうして修験道は独自の山岳を拠点にしながら、ネットワークを広げ、強力な教団組織を全国各地に形成していったのです。
戦国の世を控えて、この中から、忍者集団が生まれてきても不思議ではありませんし、そうでなくとも忍者集団と何らかの交渉があったことは否めないことだと思います。